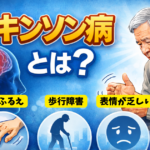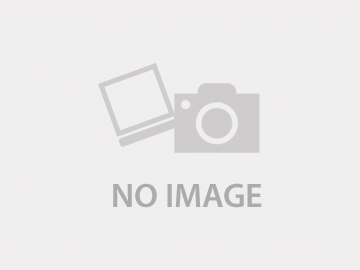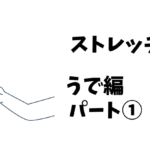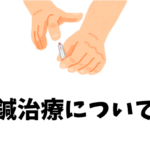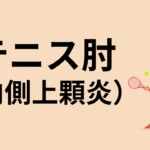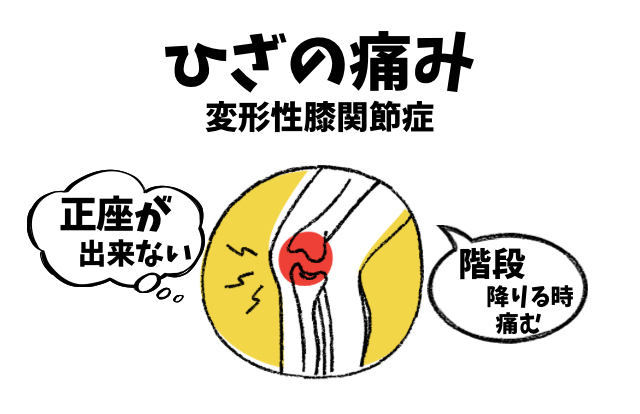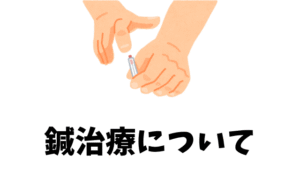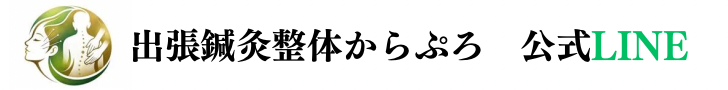胸郭出口症候群とは、頸部から分岐した神経やその近接部位を通過する血管が、胸郭出口領域という3箇所の狭窄部位で圧迫を受けることによって、神経症状や血管障害(肩こり、腕への走るような痛み、しびれ、腕や指先の冷え)が出現することをいいます。思春期以降のやせ型でなで肩の女性に多いようです。
〜病態〜
頸部から分岐した神経が狭窄を受けやすい部位は3箇所あり、狭窄を受ける部分により以下のように分類されます。
- 斜角筋症候群(第1トンネル)
- 肋鎖症候群(第2トンネル)
- 過外転症候群〜小胸筋症候群〜(第3トンネル)
前・中斜角筋および第一肋骨間によって形成される斜角筋隙(第1トンネル)で神経、血管が圧迫を受ける。先天性の異常であることが多い。
第1肋骨および鎖骨で形成される第1肋骨鎖骨間隙(第2トンネル)で神経、血管が圧迫を受ける。後天性の骨、軟部組織の異常(肋骨の骨折、なで肩などの骨格異常)が原因であることが多い。
小胸筋および肋骨で形成される小胸筋肋骨間隙(第3トンネル)で神経、血管が圧迫を受ける。後天性の骨格、軟部組織異常(小胸筋の筋緊張によるなで肩)
〜症状〜
神経症状や血管障害(肩こり、腕への走るような痛み、しびれ、腕や指先の冷え)。重症例では何をしていても慢性的に症状が出現しますが、多くの場合、吊り革を掴んでいるときなど腕を上に上げている姿勢で症状が出現します。
デスクワークやスマホ操作などで下を向くことが多いと猫背やまき肩などの姿勢不良を起こしやすく、その姿勢不良が胸郭出口症候群の原因とされています。また重たいものを持ち上げることが多いと肩周囲の筋肉が緊張し、近くを走行している神経血管を圧迫してしまうことがあります。これもまた胸郭出口症候群の原因の1つとされています。
圧迫を受けている部分の特定をして、姿勢不良が原因の場合は骨格の矯正を行い、筋肉の緊張が原因の場合はマッサージやストレッチで筋肉の柔軟性を高めていきます。筋力の低下が原因の場合はトレーニングを行う必要があります。
僧帽筋のトレーニング
菱形筋のトレーニング
小胸筋のマッサージ